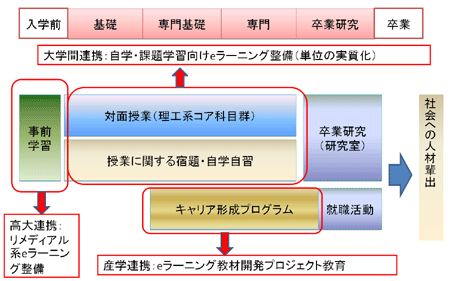 |
| 図 連携の概念図 |
特集 連携で学生を創る
小松川 浩(千歳科学技術大学総合光科学部教授)
千歳科学技術大学は、平成10年開学で1学年240名定員の理工系単科の大学です。40名弱と極めて少ない教員体制ではありますが、学力多様化に対するリメディアル教育、質保証に向けた授業・宿題含めた単位の実質化、出口の要請に基づく実践的キャリア教育の実施など、現代の教育改革に呼応した幅広い教育サービスを実践しています。少ない人員で多様な教育サービスの提供を図るため、ICTを活用した効率的・効果的な教育サービスの実施が重要と考えています。特に、eラーニングの取り組みには力を入れています。理工系の基礎知識の定着を図るためのリメディアル系教育では、演習を中心に反復的に取り組めるシステム的な工夫を施し、自分のペースで自学自習できる環境を整備しています。学習素材としては、後述する地域連携の枠組みを活用して、中学校から高校までの数学・理科・英語等の体系的な教材の整備を図っています。専門教育については、本学専任教員による教材の整備を進め、授業の課題や宿題でのeラーニング活用や、補講のeラーニングでの置き換え(学習管理を伴う学習時間の担保)を実施しています。また、情報処理などの資格対策を中心としたキャリア系講義は、講義自体をeラーニングに置き換え、学生に自律的な学習を促すようにしています。こうした取り組みは、FDと連動する枠組みで検討し、試行を踏みながら進めています。これは、授業の手を抜くための効率的なeラーニング利用ではなく、効果的な学習効果を生むためのeラーニング活用を前提とするためです。例えば、初年次基礎教育の英語では、20以上のコースをeラーニング上で展開し、学力の多様化した学生一人ひとりを上手にコントロールしながら、自分に合ったコースを自律的に学ばせる取り組みを実施しています。また数学では、学習管理機能を活用して学習でつまづいている学生を見つけ出し、対面の個人指導室で対応を図るなどしています。こうした取り組みは、eラーニングを活用することで効率的・効果的に実践できた事例と考えています。また、高校と連携した高校生への遠隔型単位認定や他大学との連携を通じた遠隔科目の設定も行われ始めており、多様な学習サービスの提供が図れるようになってきました。
本学でのeラーニングの取り組みの最大の特徴は、教材開発が学生の(情報系)教育プログラムの一環で行われている点にあります(持続可能な教材開発)。入学後の初年次教育では、多くの学生がeラーニングを活用して勉強を行います。すなわち、この段階では彼らは、システム利用者(ユーザ)と位置づけられます。そうしたユーザに対して、1学年の情報系の必修授業で、本学のeラーニングがすべて学生チームで構築されている事実や情報系の取り組みのチーム開発の重要性を教えます。本学では学科配属は2年次以降ということもあり、こうした内容を含めて情報系に興味を持った学生が該当学科に希望を出します。そして、学部2年生を対象とした情報系のプロジェクト教育に参加します。このプロジェクトでは、顧客のニーズを把握して、情報システム(コンテンツ)を開発して、これを評価する内容となっています。eラーニング教材の開発では、授業実践を希望する教員を顧客と見立て、この顧客のニーズに基づく教材開発を行い、実際に授業と連携してeラーニングを活用するという内容となっています。この時点で、学生はユーザから開発者への意識の転換を求められます。なお、プロジェクトは、一部の3年生がプロジェクトリーダ役として参加して行われるようになっており、日頃の教材開発のスキルは、こうした先輩から教わりながら進めていきます。また教材開発は、PDCAサイクルに基づく複数年次の取り組みが重要となります。ここで、本プロジェクトでは複数学年の学生が参加する体制となっているため、ノウハウも毎年引き継がれる仕組みとなっています。そこで、顧客として参加する教員も、毎年教材の改良を行うことも可能となり、結果的に授業改善にも寄与する内容となっています。なお、一部の3年生(毎年20名程度)は、本学の情報教育メディアセンターでTA的に任用されており、実質的な教材開発は、こうした学生によって行われています。開発した教材については、対価が支払われると同時に著作権の処理が行われ、本学の授業で活用する教材として公開される仕組みとなっています。
顧客として参加する教員とは別に、一連の学生プロジェクト教育を担当する教員がいます。この教員は、非常に重要な役割を演じており、いわゆるプロジェクトマネージメント(PM)役をこなしています。しかし、元来大学の教員が、チームを組んで物事を達成していくプロジェクト経験を持っているとは限りません。そこで、本学では積極的にSI系の企業の方にプロジェクト教育にコミットしていただく雰囲気作りに努めています。企業との繋がりは、研究室レベルでの共同研究や、就職部を通じた人材交流的な位置づけなど、いくつかのチャネルがあります。最近では、実際に学生プロジェクトの成果内容(開発コンテンツ)に興味を持つ企業が、実質的な共同研究の延長線上で学生プロジェクトにコミットしてくる事例も生まれてきました。また、学生プロジェクトに参加した学生自体がベンチャーを立ち上げ、これを参加企業がバックアップする形で実ビジネス的な拡がりを持った連携も拡がりつつあります。現在、7団体が何らかの形でプロジェクト教育に参加いただいています。こうした企業の存在は、学部2年次からプロジェクトに参加する学生に見せる出口という意味で、学生にとっても大変良い刺激となっています。
教材の開発という部分では、大学の教員だけではなく、高校の教員との連携の下でも進められています。具体的には、リメディアル系(入学前教育と初年次の補習教育)で必要となる高校の教材開発については、顧客役となる先生を高校の先生にお願いして、本学の教育プログラムに参加していただいています。一方で、開発された高校教材(数学・英語・物理・化学・生物)は、大学と高校双方の教育で活用することで、相互に意味のある高大連携を築いています。最近では、高校生にも夏休みに実際の教材開発プログラムに参加してもらい、このプロジェクトのリーダ役を本学の大学生が担当するようなイベントも開催しています。現在、北海道内の連携校は、24校となりました。また、同様の枠組みで千歳市教育委員会との連携の下、小中学校の教員とも連携して、小中学校の教材開発を進めています。こうした教材は、高校でのリメディアル教育でも積極的に活用されたり、高校と中学校の授業研修で利用されたり、小中高大連携の取り組みへと広がりつつあります。本学のFDという観点では、高校と大学の教員合同による教材開発研究会(ICT活用教育研究会)を毎月開催して、初年次教育に関わる教育方法の意見交換を図っています。大学の教員は、高校教育の現状や問題点を把握した上で入学してくる学生への指導を検討する良い機会となっています。
最近では他大学との連携も推進しており、こうした教員も研究会に参加し、教材開発のミーティングを通じて、大学間での授業方法の改善検討を図っています。札幌近隣では、現代GPの枠組みで医療系の教材開発を行っていた札幌医科大学(道立)とは、教材の相互利用実験を開始しています。また、文系の教材開発については、北星学園大学(私立)と包括連携の下で進めており、心理学や憲法などの教材の開発を行い、遠隔型の授業実践の取り組みを試行しています。こうした取り組みでは、各大学が保有する教材を如何に共有していくか、相互に異なるシステムをどのように連携させるか、学生教育という共通項において如何にノウハウを共有していくかなど、各大学の主体性を前提にした上での「緩やかな大学連携」が重要と考えています。そこで、eラーニングを積極的に推進している大学が発起校となり、大学eラーニング協議会を立ち上げ、情報の共有を図っています。平成21年度は、本学が代表校となっていますが、約20の大学にご参加いただき、個別の大学間の連携を模索している状況です。こうした取り組みを通じて質の高い教材が共有されれば、産学連携の枠組みを利用したコンテンツ流通・新しい教育支援サービスの創出にも繋がるのでは期待しています。
図 連携の概念図
本学のeラーニングを介した学生教育の実践と学内FDの取り組みは、約10年近く継続されている状況にあります。こうした継続的な取り組みを行うには、大学内部の理解と、外部との連携が結果的には不可欠と認識しています。連携については、その契機は担当者レベルでのボトムアップ的な活動が基本となりました。一方で、どこかのタイミングで組織的な枠組みとすることも重要で、これについては、本学では学長のトップダウンが大きく機能しました。内部的・外部的にも、推進していく大義名分としての共有可能なキーワードは重要であったと考えています。外部との連携では、「成果の共有」が重要なキーワードとなりました。開発される「教材コンテンツ」や運用を通じた「教育ノウハウ」の共有は、時と場所を越えて共有可能な成果として、非常に重要な連携条件であったと思います。一方、学内でのコンセンサスという点では、「人材育成」が重要なキーワードになりました。我々の取り組みでは、eラーニングの教材開発の学生プロジェクトに、高校・他大学・企業が関わるという形で、まさに人材育成のための連携となるように意識しました。これは、本学が継続的にeラーニングの取り組みを実施できた最大の原動力となったと考えています。