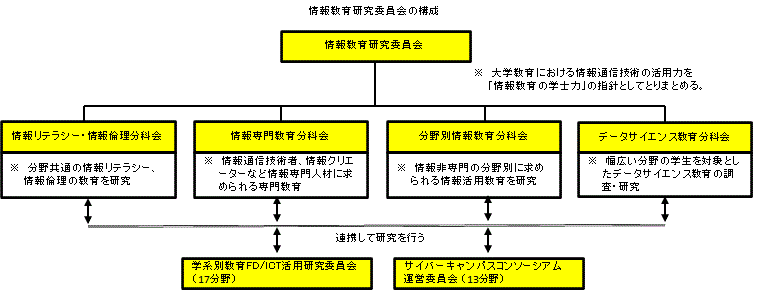① 社会で求められる情報活用能力育成の研究と理解の促進
高校の必履修科目「情報Ⅰ」と大学情報教育の接続が円滑に対応できるよう、プログラミング・アルゴリズム関連の教材及び教育方法、モデル化・シミュレーション関連の教材及び教育方法、データサイエンス・AI活用教育に向けた教材及び教育方法の事例を整備しつつある。以上の活動を効果的に進めるため、「情報活用教育コンソーシアム」のプラットフォーム上で関係教員によるシンポジウムや意見交流の機会を設け、コンテンツ利活用の促進に向けた紹介活動、生成AIを使いこなす授業方法、著作権法などの対応事例を収集・紹介する。
② 仮想空間を活用した教育のオープンイノベーションの研究
学生が取り組んでいるSDGsの研究を仮想空間の上で企業・自治体に紹介し、興味・関心があればマッチングして、個別に当事者同士でPBLを展開するオープンイノベーションを本格的に進めていくためのパイロットプランをとりまとめ、実施に向けた準備への対応をすすめるため、情報専門教育分科会に「メ
タバース・VR教育利活用小委員会」を継続設置する。
③ データサイエンス・AI教育を支援する研究
本協会の「大学における数理・データサイエンス・AI教育支援プラットフォーム」に文部科学省で認定したリテラシーレベル、応用基礎レベルの先導的な「プラス」認定校の情報を更新・掲載するとともに、リテラシーレベル、応用基礎教育レベルのワークショップを行い、学生が意欲的に取り組むような授業運営の工夫、教材などの支援について研究し、理解の促進を図る。
|